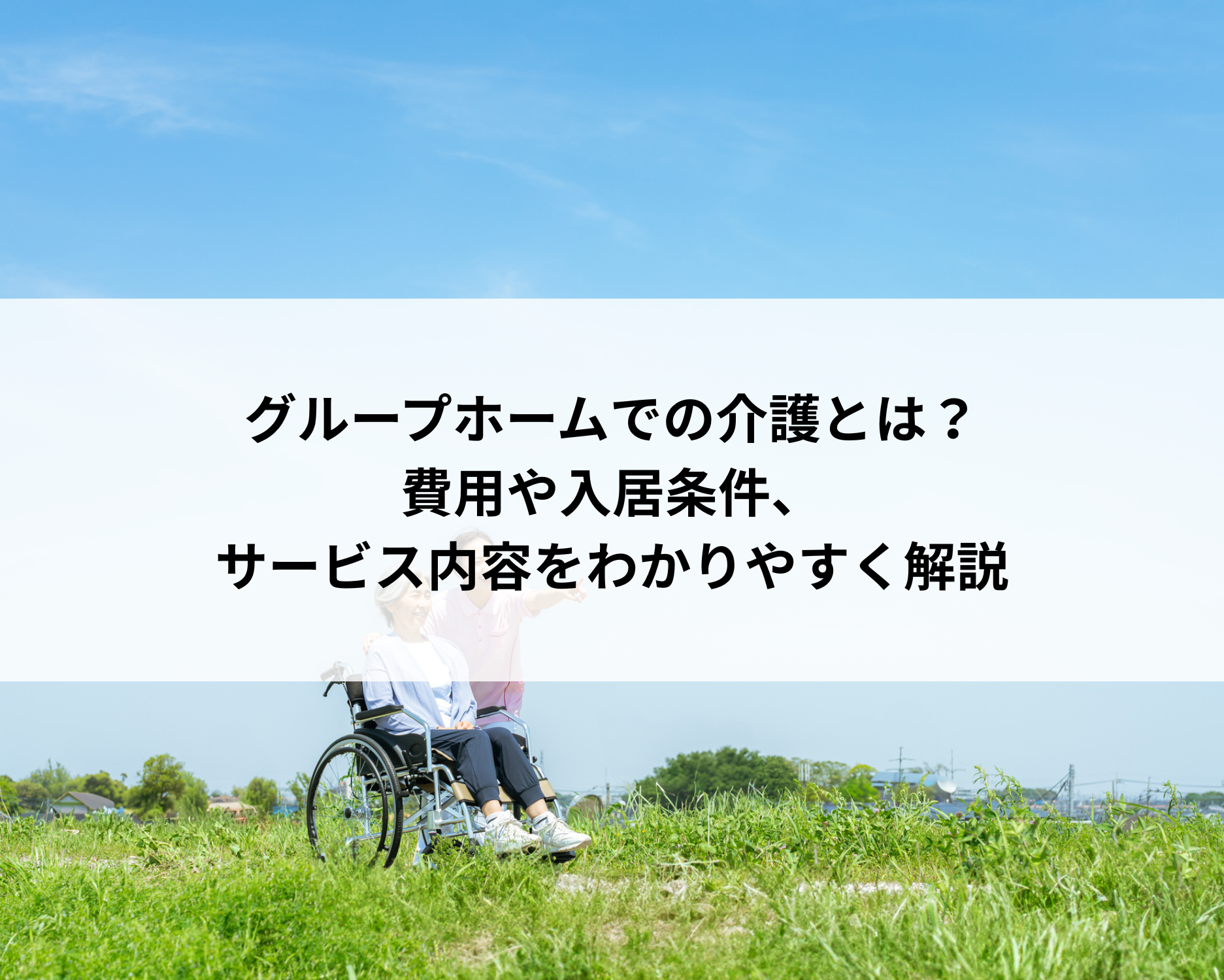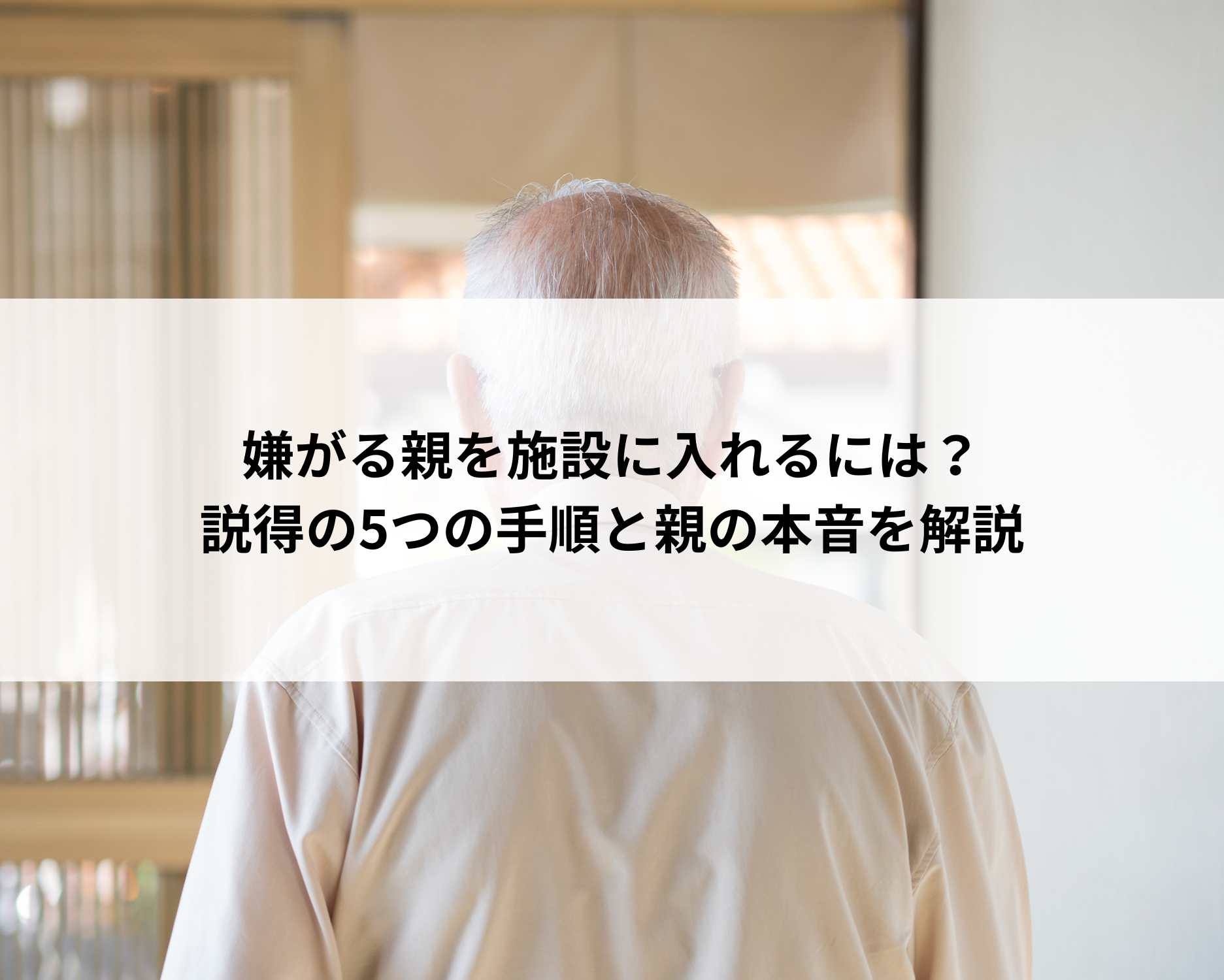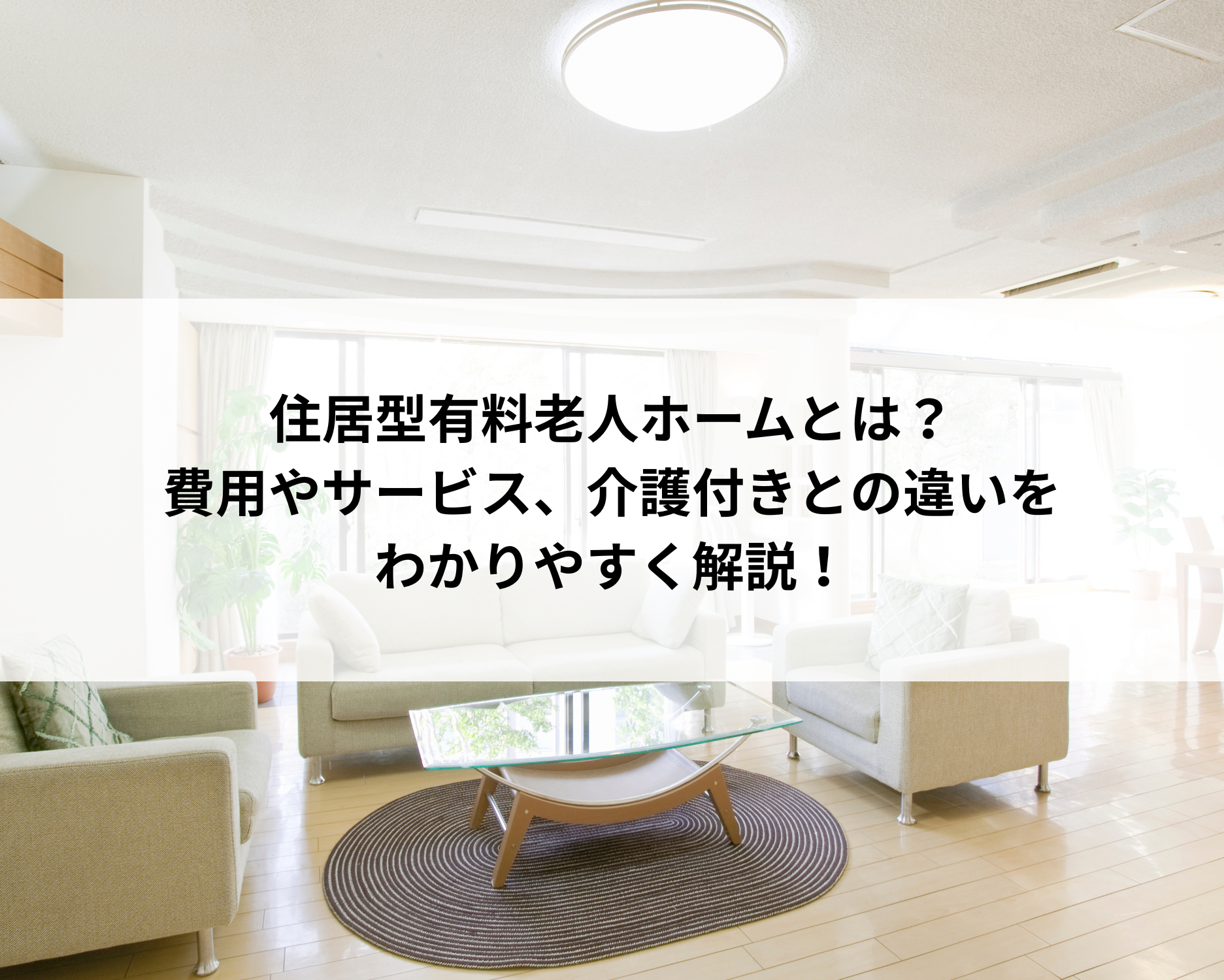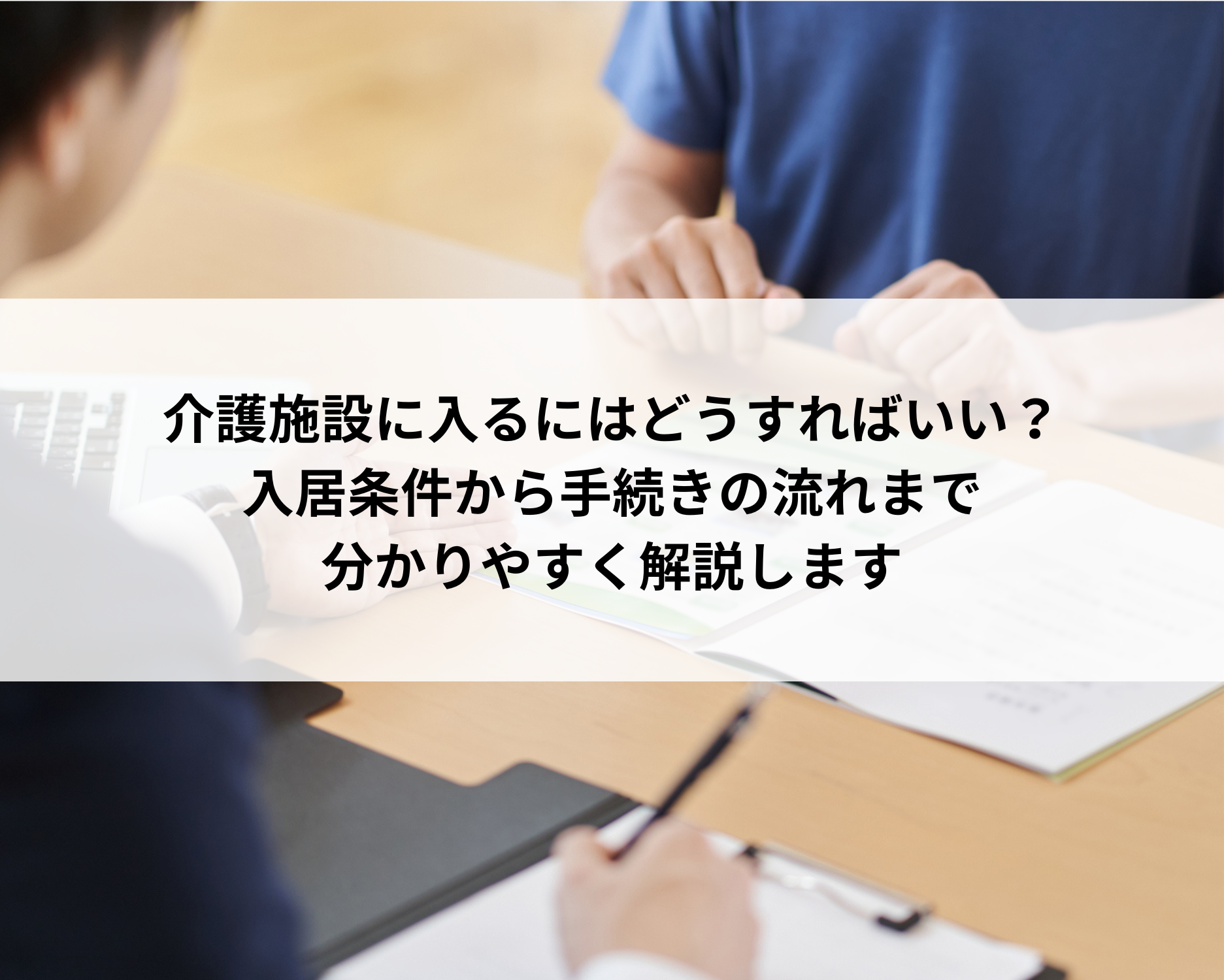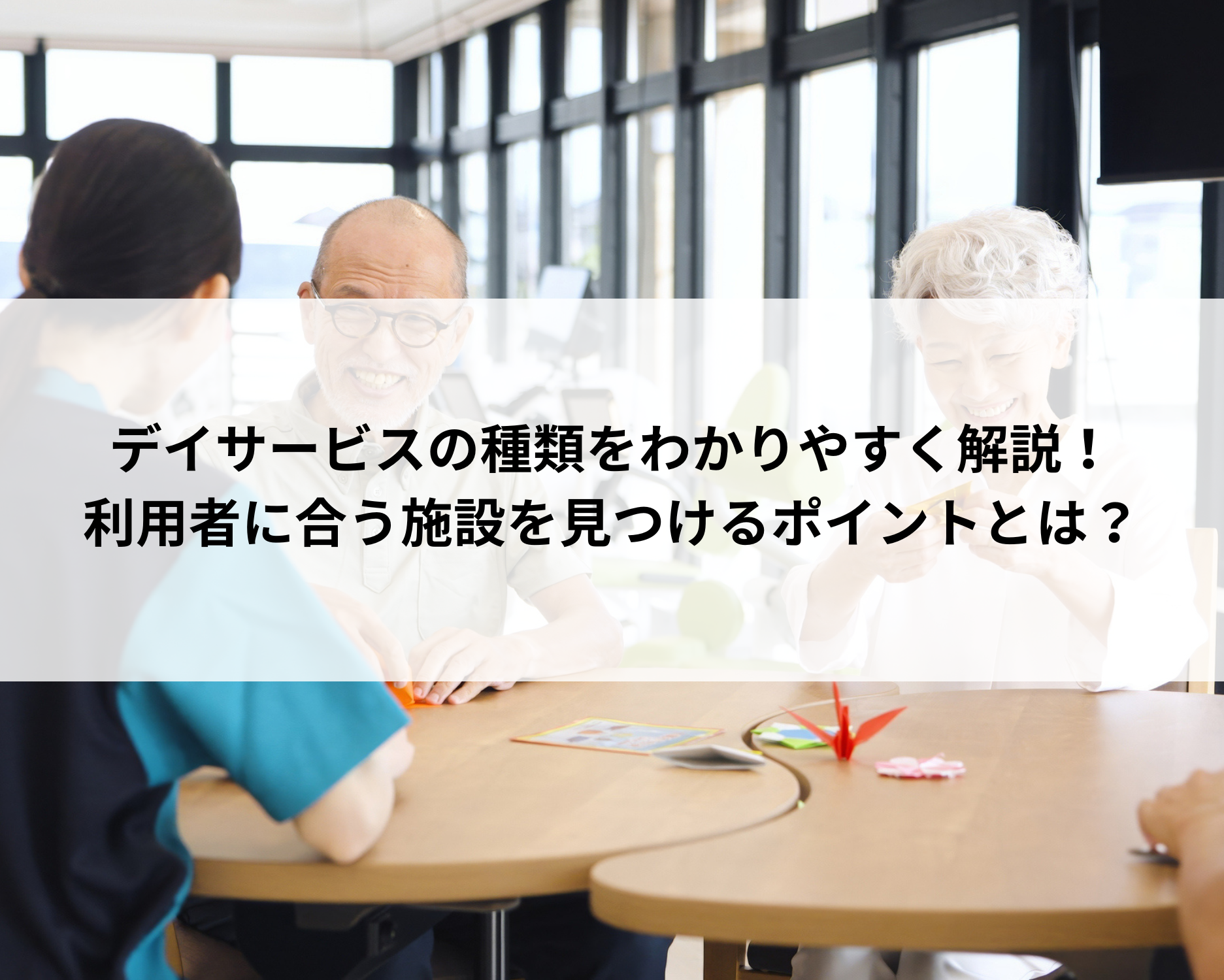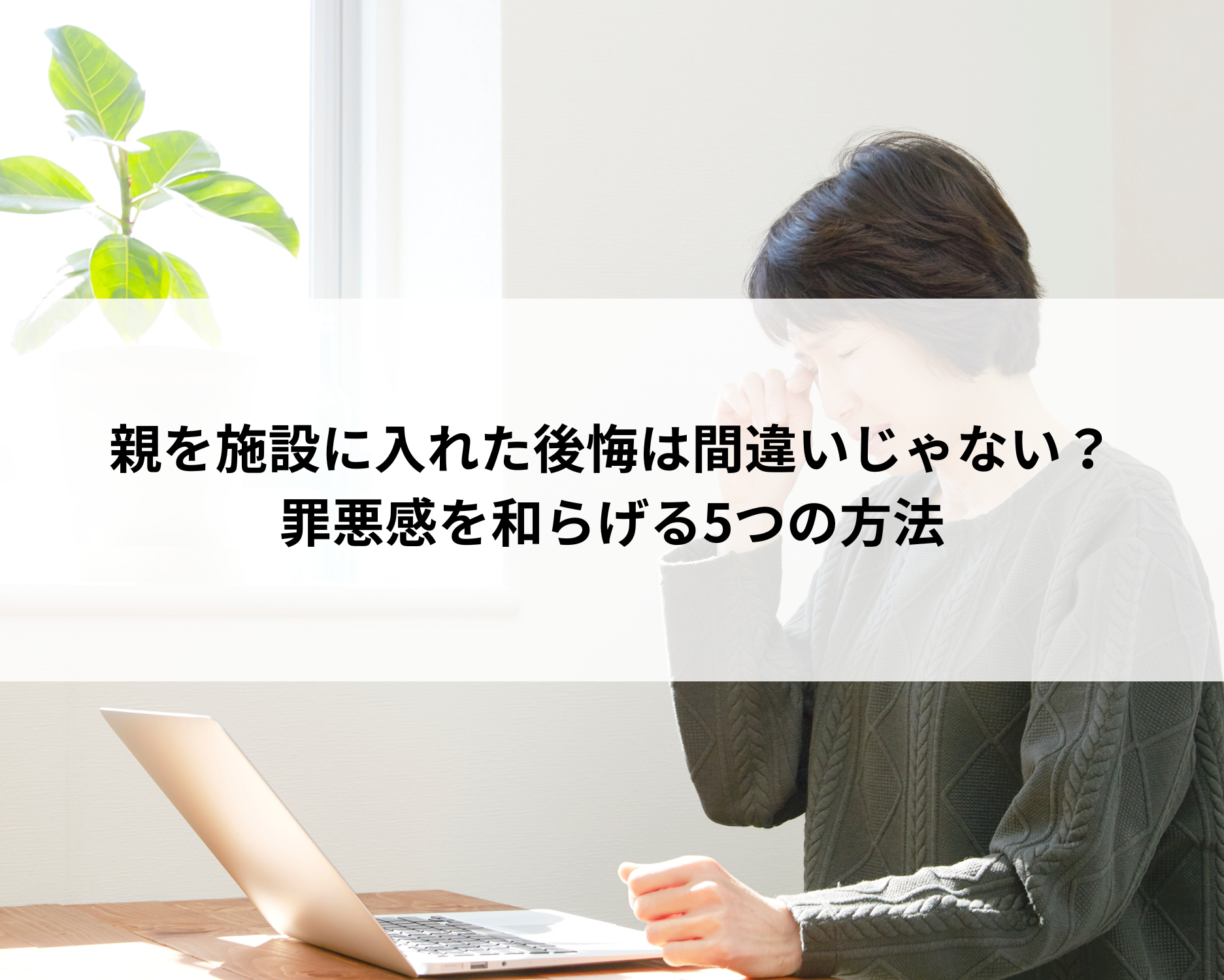在宅介護とは?サービスの種類から費用、始め方までわかりやすく解説します
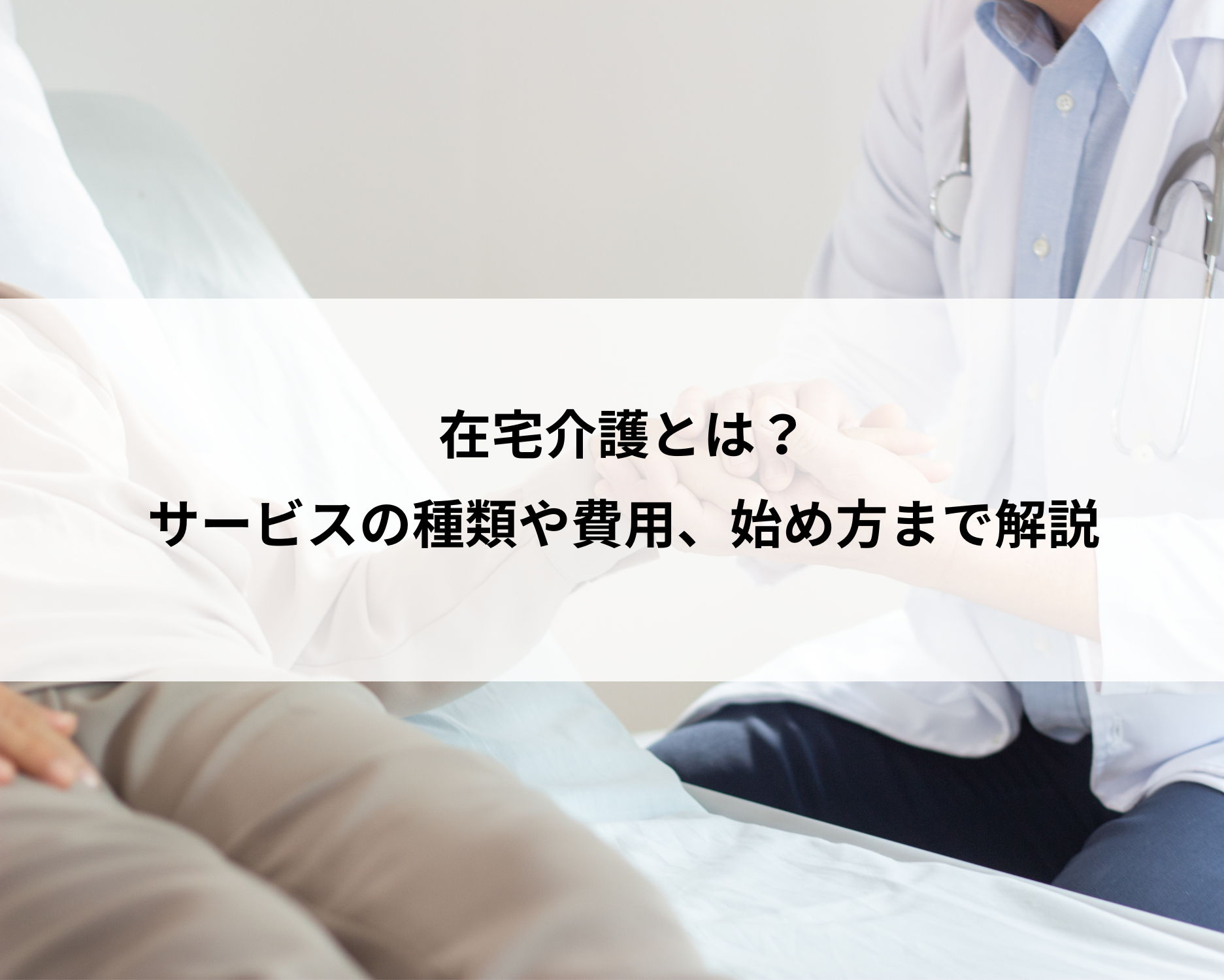
ご家族の介護が必要になったとき、「住み慣れた自宅で過ごさせてあげたい」と考える方は多いのではないでしょうか。この記事では、在宅介護の基本的な知識から、利用できるサービスの種類、費用の目安、そして実際に始めるための手順まで、わかりやすく解説します。在宅介護を検討されている方や、すでに介護をされているご家族の負担を少しでも軽減し、安心して在宅介護を続けられるための一助となる情報をお届けします。
在宅介護とは?自宅で受けられる介護の基本

在宅介護とは、文字通り、高齢者や障害を持つ方が、施設に入所するのではなく、ご自身の住み慣れた自宅で生活を続けながら介護サービスを受けることです。多くの方が望む「最期まで自宅で」という願いを叶えるための選択肢の一つとして、近年ますますその重要性が高まっています。
在宅介護の定義と対象者
在宅介護は、要介護者や要支援者が自宅において、日常生活の支援や医療的ケア、リハビリテーションなどを受けることを指します。対象となるのは、主に介護保険制度における要支援1・2、または要介護1~5の認定を受けた方です。病気や怪我、加齢などにより、一人での生活が困難になった方が、専門家のサポートを受けながら自宅での生活を継続することを目的としています。身体的な介護だけでなく、精神的なサポートや生活環境の整備も含まれる点が特徴です。
在宅介護で利用できる主なサービスの種類と内容

在宅介護を支えるサービスには、介護保険が適用されるものと、適用されない保険外サービスがあります。それぞれの特徴を理解し、ご本人の状態やご家族の状況に合わせて適切に組み合わせることが大切です。以下に代表的なサービスの種類と内容を紹介します。
| サービス区分 | サービス | 内容 |
| 訪問サービス | 訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護 | 食事・排泄・入浴介助、健康管理、医療的ケア、リハビリ、安否確認など |
| 通所サービス | デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション) | 食事・入浴、機能訓練、レクリエーション、他者との交流、健康チェックなど |
| 短期入所サービス | ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護) | 一時的な宿泊、食事・入浴・排泄介助、機能訓練、家族の介護負担軽減(レスパイト) |
| 地域密着型サービス | 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問・通い・泊まりを柔軟に組み合わせたサービス、24時間対応の訪問サービスなど |
| 福祉用具 | 福祉用具貸与(レンタル)、特定福祉用具販売(購入) | 車いす、介護ベッド、手すり、歩行器などのレンタル、ポータブルトイレなどの購入 |
| 介護保険外サービス | 民間の家事代行、配食サービス、見守りサービス、外出付き添いなど | 介護保険でカバーできない家事支援、食事の提供、安否確認、趣味の外出支援など |
訪問サービス:自宅に来てもらう
訪問サービスは、ヘルパーや看護師などの専門職が利用者の自宅を訪問し、必要なケアを提供するものです。代表的なものに「訪問介護」があり、食事や排泄、入浴などの身体介護や、掃除、洗濯、調理などの生活援助を行います。「夜間対応型訪問介護」は、夜間の定期的な巡回や緊急時の対応を行うサービスです。これらのサービスにより、住み慣れた自宅での生活を継続しやすくなります。
在宅介護のメリット

在宅介護には、施設介護とは異なる多くのメリットがあります。ご本人にとっても、介護するご家族にとっても、より良い選択となる可能性があります。
要介護者にとってのメリット
まず、ご本人にとって最大のメリットは、何と言っても「住み慣れた環境で生活を継続できる」ことです。 また、生活リズムを大きく変える必要がなく、近隣住民との関係も維持しやすいです。個別のケアプランに基づき、一人ひとりの状態や希望に合わせたきめ細やかなサービスを受けやすい点もメリットと言えるでしょう。家族が近くにいる安心感も、ご本人にとってはかけがえのないものです。
介護する家族にとってのメリット
介護するご家族にとっては、大切な家族のそばにいられる時間が確保できることが大きなメリットです。日々の変化に気づきやすく、コミュニケーションも取りやすいでしょう。
在宅介護のデメリットと注意点

在宅介護は多くのメリットがある一方で、デメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、無理のない在宅介護を続けるために重要です。
要介護者にとってのデメリット・注意点
ご本人にとってのデメリットとしては、日中の家族が不在の場合などに孤独感を感じやすいことや、社会との接点が少なくなりがちな点が挙げられます。デイサービスなどを利用して他者との交流機会を持つことが大切です。また、医療依存度が高い場合や容体が急変しやすい場合は、24時間体制の医療的ケアが難しい場合があり、家族の不安が大きくなることもあります。緊急時の対応体制を事前に確認しておくことが重要です。
介護する家族にとってのデメリット・注意点
介護するご家族にとって最も大きな課題は、やはり精神的・肉体的負担の大きさです。特に、介護の中心となる方が一人に偏ると、その負担は計り知れません。「24時間介護」というプレッシャーを感じ、自分の時間が持てなくなることもあります。介護のために仕事を辞めざるを得ない「介護離職」のリスクも考慮する必要があります。
在宅介護にかかる費用はどのくらい?内訳と目安

在宅介護を検討する上で、費用は非常に気になるポイントです。介護保険サービスの自己負担額、保険外サービスの費用、その他雑費などを考慮する必要があります。
| 要介護度 | 支給限度基準額(1ヶ月あたり)※1 | 自己負担額の目安(1割負担の場合) |
| 要支援1 | 50,320円 | 約5,032円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 約10,531円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 約16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 約19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 約27,048円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 約30,938円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 約36,217円 |
| ※1 2024年4月時点の標準地域の単位数に10円を乗じた概算。地域やサービス内容により異なります。正確な情報は市区町村やケアマネジャーにご確認ください。 |
介護保険サービス利用時の自己負担額
介護保険サービスを利用した場合、費用の原則1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)が自己負担となります。ただし、要介護度別に1ヶ月あたりの利用できるサービス量の上限(支給限度基準額)が定められており、これを超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。上の表は、その支給限度基準額と、限度額内でサービスを利用した場合の1割負担の目安を示したものです。実際の費用はケアプランの内容によって変わります。
引用元リンク:参照元:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
在宅介護を始めるための手順と流れ

在宅介護を実際に始めるには、いくつかのステップを踏む必要があります。慌てずに、一つひとつ進めていきましょう。
手順1:相談窓口で相談する
まず最初のステップは、専門の相談窓口に相談することです。市区町村の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターが主な相談先となります。
ここでは、介護に関する悩みや疑問、利用できるサービスなどについて全般的なアドバイスを受けることができます。現在の状況を伝え、どのような支援が必要か相談してみましょう。相談は無料です。
手順2:要介護認定の申請をする
在宅介護サービス(介護保険サービス)を利用するためには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。申請は市区町村の窓口で行います。申請書や介護保険被保険者証、主治医の意見書(市区町村が手配する場合もあります)などが必要です。
申請後、認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行います。この調査結果と主治医の意見書をもとに審査が行われ、要介護度が決定されます。結果が出るまでには通常1ヶ月程度かかります。
手順3:ケアプランを作成する
要介護認定の結果が出たら、ケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼します。ケアマネジャーは、ご本人やご家族の希望、心身の状態、生活環境などを考慮し、どのようなサービスをどのくらい利用するかを盛り込んだケアプランを作成します。このプランに基づいてサービスが提供されるため、しっかりと要望を伝えることが重要です。ケアプランの作成費用は全額介護保険から給付されるため、自己負担はありません。
手順4:サービス事業者と契約し利用開始
作成されたケアプランに基づき、利用するサービス事業者を選定します。ケアマネジャーが複数の候補を紹介してくれるので、サービス内容や雰囲気などを比較検討し、ご本人に合った事業者を選びましょう。事業者と契約を結んだ後、いよいよサービスの利用が開始されます。サービス開始後も、定期的にケアマネジャーが状況を確認し、必要に応じてケアプランの見直しを行います。
在宅介護を支える家族の心構えと負担軽減策

在宅介護は、ご家族の協力なしには成り立ちません。しかし、介護する側が疲弊してしまっては元も子もありません。無理なく続けるための心構えと負担軽減策を知っておきましょう。
完璧を目指さない介護
介護において、「完璧」を目指す必要はありません。すべてを一人でこなそうとしたり、理想通りにいかないことにストレスを感じたりすると、精神的に追い詰められてしまいます。「できる範囲でやる」「手抜きも時には必要」と考える柔軟性が大切です。頑張りすぎず、息抜きをすることも忘れないでください。
介護サービスの積極的な活用
利用できる介護サービスは積極的に活用しましょう。訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを利用することで、介護者の時間的・身体的負担が軽減されます。特にショートステイは、介護者の休息(レスパイトケア)のためにも有効です。 「人に頼るのは申し訳ない」と思わず、専門家の力を借りることは、より良い介護のためにも必要なことです。
在宅介護に関するよくある質問
Q1. 認知症でも在宅介護は可能ですか?
A. はい、可能です。認知症の症状や進行度に合わせて、訪問介護やデイサービス、グループホーム(地域密着型サービスの一種)などを利用することで、在宅での生活を続けることができます。 徘徊や物盗られ妄想などの症状がある場合は、専門医やケアマネジャーとよく相談し、適切な対応策やサービス利用を検討することが大切です。環境整備や家族の理解も重要になります。
【内部リンク】認知症予防につなげる音楽の力 3選! | 【公式】バナナ園グループ
Q2.急に介護が必要になった場合、どうすれば良いですか?
A. まずは、お住まいの地域の地域包括支援センターに相談してください。緊急の場合でも、状況に応じて必要なアドバイスや、利用できるサービスの案内をしてくれます。 例えば、一時的にショートステイを利用したり、迅速に要介護認定の手続きを進めたりするなどの対応が考えられます。病院からの退院で急に介護が必要になった場合は、病院の医療ソーシャルワーカーも相談に乗ってくれます。
Q3. 仕事と介護の両立はできますか?
A. 簡単ではありませんが、工夫と周囲のサポート次第で可能です。介護休業制度や介護休暇、短時間勤務制度などを勤務先が設けている場合は活用しましょう。 また、デイサービスやショートステイなどの介護サービスを上手く組み合わせることで、仕事の時間を確保することもできます。一人で抱え込まず、ケアマネジャーや職場、家族とよく相談し、無理のない両立プランを立てることが重要です。
まとめ:安心して在宅介護を続けるために
在宅介護は、ご本人にとってもご家族にとっても、多くのメリットがある一方で、様々な課題も伴います。介護者自身の心身の健康も大切にしながら、無理のない在宅介護を続けていくことが何よりも重要です。